
1991年一本の映画の製作開始の発表が、ハリウッド・ワーナーブラザーズ社であった。監督は、”プラトーン”や”7月4日に生れて”などの社会派映画の巨匠としてその名前を定着させ、オスカー受賞監督でもあるオリバー・ストーンである。そして、主演者には大物俳優のケビン・コスナーがあてられている。しかし、この映画製作が発表されてからのマスコミや政府の意向を受けたと思われる人々の張った映画批判の一大キャンペーンは、まさに、狂気といってもいいほどの熾烈なものであった。特に世界的にも、高級紙として認知されている、”ワシントンポスト”や”ニューヨークタイムズ”の張ったキャンペーンは、「どうしてそこまで、やらなければならないのか?」と思わせるものであった。それは、単に作品を批判し、その評判をおとしめる事にとどまらず、まさに映画そのものの”撲滅”を図るようなものであった。その端緒となったのが、1991年5月19日ワシントンポストに発表された”不思議の国のダラス”と題した署名入りの記事であった。署名者は、ジョージ・ラードナー・Jrである。この記事以降一年間というもの、全アメリカはほとんどのマスコミが動員された感
があった、批判の掲載に対してその反批判が繰り返され、著名な人物(元合衆国大統領)や著名なケネディ暗殺研究者(単独犯行批判者)のほとんど統べてがこの論争に加わった。一本の映画の製作がついにはケネディ暗殺事件の真相究明の場にまで発展したのであった。論争の原点はその主なストーリーの元になっている、ニューオリンズ地方検事ジム・ギャリソンの著書”JFK・ケネディ暗殺犯を追え”の評価に起因する。さらにはその著書の元になっている「クレイ・ショー裁判」の評価も巻き込み、ウオーレン委員会の評価おも含めて論争されたのである。
ケネディ暗殺事件が映像化されたのはこの映画が決して最初ではない、ドナルド・フリード、マーク・レーン共著の”ダラスの熱い日”を映画化した、同名の映画がすでに20年前に発表されている、主演は当時では最高の俳優といわれたバート・ランカスターである。この作品は、元CIAの職員に扮するバート・ランカスターが、テキサスの大富豪のバックアップにより狙撃者の訓練から逃亡までを指揮して暗殺を実行していく過程が画かれている(このページをじっくり読んでいただいた方にはこの二人が誰であるのかお分かりですね。)この時には今回のような大論争が巻き起こったと言う話しは聞いていない。すなわち、今回の大論争の本質的な論点はジム・ギャリソン検事の起こした「裁判」の評価に他ならない。
この項目では映画に映し出されたプロセス、事実関係に関しての紹介はしない。なぜならこのストーリーこそが現在ケネディ暗殺事件研究の主流をなす出来事・疑問を紹介しながら物語りが構成されて進んでおり、ほとんどの出来事・疑問は本ページのいずれかで紹介、検討されている事項である、又ギャリソンの起こした「クレイ・ショー裁判」自体が本ページの主要コンテンツとして計画され準備されているからである。
この、大論争(映画に画かれた数々の事実・仮定・言葉に関する批判、反批判は別として)の論旨をもっとも要約したのは、1991年12月26日付のシカゴトリビューン紙の社説であろう。社説は次のように解説する・・・
危険なのは、ストーンの映画とそこで実に効果的に描かれる偽りの歴史が一般に受け入れられる見解になるであろうと言うことだ。とどのつまり、どんな学識がコスナーやサ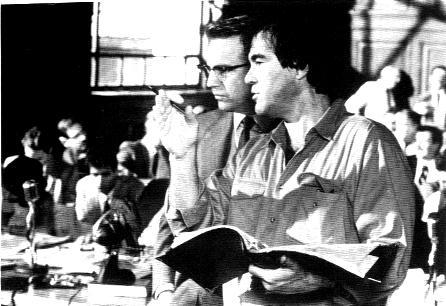 ザーランド、その他のスター達の役にたてるのか?たとえば、現実に陰謀が存在し、それがギャリソン/ストーンが割り出したものでなかったらどうであろう? ザーランド、その他のスター達の役にたてるのか?たとえば、現実に陰謀が存在し、それがギャリソン/ストーンが割り出したものでなかったらどうであろう?
だから、今こそ、ケネディ暗殺事件に関する証拠文書とすべての物的証拠”映画・フィルム・組織標本・等々”を公開し調査に役立てられるようにしなければならない。来世紀をかなり過ぎるまでこれらの事柄を秘密にしておく事について、絶えず二つの懸念が取り沙汰される。ケネディ家の感情と、アメリカの国家安全保障がソ連と比較して損なわれるのではないかという不安である。
いずれもかつては障害になって当然だったとしても、今日障害になるはずはない。1963年11月22日以降、我が国の歴史が何かを立証しているとしたら、それは一般公開による浄化効果と秘密主義による腐敗効果である。
さらに、映画人であるロジャー・エバート氏は、次のように述べる。
ワシントンポストやニューヨークタイムズなどの、この映画に対する一種感情的な批判は、つまるところすべて二つの要点に行き着く、ストーンの映画が、立証できぬ推測に基ずいていると考えられていたこと、そして、この映画の主人公で元ニューオリンズの地方検事ジム・ギャリソンが、何もないところからクレイ・ショー相手に訴訟を起こした不徳の売名者と信じられていたことである。
以上の要点は確かにもっともらしく受け取られるが、映画には無関係だと私は思う。これはドキュメンタリーでも歴史研究でも法廷劇でもなく、ケネディ暗殺をめぐる神話、殺された指導者がおぞましい陰謀の犠牲者であるという神話をおり込んだ映画なのである。・・・・人々はストーリーを知りたいから映画を見に行く、内容がすぐれているのであれば、映画が続く限りそれを信じるものである。ストーリーテリングの見事な実例と私個人が考える「JFK」の場合、観客が覚えているのは、主人公が孤独の作戦行動で暗殺を解明する為に展開させる事実と憶測ではない。彼らの心に残るのは(まだ若い観客であるのなら学ぶことは)、1963年11月22日にわれわれ国民がどう感じたか、そして、以後の年月、一つの嘘、すなわちケネディの暗殺犯についての真相をわれわれが知っていると言う嘘が、どうして国民の喉元でつかえているのか!ということである。・・・・ニューズウイークは、ドキュメントドラマの形態にありがちな落とし穴を警戒して、「本物のドキュメンタリー・シーンと再構成されたシーンを見分けることのできるのは注意怠り無い、ごく一部の観客のみである。」と懸念をあ
らわにしている。確かにそれは事実である。しかし同誌は、凶器のライフルに、警察官がオズワルドの遺体の指紋をおしつけるシーンを警告をこめて引用する。観客、いいかえれば国民を馬鹿にするのもいい加減にしてもらいたい、証拠を捏造するところを警察が撮影させるなどと信じるような馬鹿が、いったいどこにいるというのだ!
1991年12月20日、映画「JFK」は一般公開された、しかし、この論争はとどまるどころか以前にも増して活発となり全米をまきこんでいったのである。このかん当事者であるオリバー・ストーンはその都度批判にたいして堂々と反論を繰り返している。そしてこの間、彼の論旨のなかには、もっとも簡単な言葉、すなはち”これは、映画なのだ!”との言葉は一切口にだすことはなかった。彼の映画に対する姿勢をうかがわさせる事であるが、まさにこの一点に現代の映像文化の功罪が存在すると思う。
この映画の製作には、数々のアドバイザーが参加している。著名なケネディ事件研究家であるマーク・レイン、ドナルド・フリード。パークランドメモリアル病院で、当時実際に大統領の処置にあたった医師、さらに映画にもX大佐として登場するフレッチャー・ブラウティー元大佐、さらにはジム・ギャリソン本人(彼はウオーレン委員長の役で映画にも出ている。)ところが、これらの制作協力者のうち数名は、その制作過程でその任から離れていったのも事実である。
かの大統領を実際に処置した医師は、そのシーンの撮影場面の考証を依頼されスタジオでストーンと激論となり、去っていった。
処置室のシーンを、メス一本にいたるまで忠実に再現したいとのストーンの依頼に対して彼は誠心誠意協力していた、ところが撮影にはいると、処置する医師団(当の本人役の俳優も含めて)の衣装は血にそまり真っ赤になっていた、すかさず、彼はこう言った”いや、その時われわれの服はまったく血液に染まる事はなかった。”と。その時ストーン監督はこう言ったという・・・・”先生、観客は血を好むんですよ、きれいなままでは迫力がありませんからね。”・・・・
さらに、マーク・レーンもそのスタッフから去っていった一人であるが、かれは、後にこう書いている。

ドナルドと私は脚本の草稿段階から協力した、しかしそれは暗殺についての事実に基ずくドキュメンタリードラマを意図していた。私にとっては、初めてのハリウッド経験であったがまもなく、銀行や保険会社、スタジオ、プロヂューサーらが映画製作を決める際には、娯楽性の方が事実より優先されることを理解した。映画作りはビッグビジネッスであり、投資に対する配当がしばしば、最も重視されるのである。
その後われわれの事実に基ずいた努力がどう扱われたを理解したので、フリードと私は製作者に個人的に、また記者会見で公式に誤りを指摘して抗議した。ストーンはわれわれの仕事に関心を持っていたが、残念ながら彼は映画の娯楽性を高める為に事実を修正ないしは変更する権利を留保していた。その為、われわれはそれ以上の交渉を断った。以前の条件は、私が掘り起こした資料を彼が自由に使えるとの権利に基ずいていたからである。その後、実際の脚本を読んだが、非常に重大な謎を解明しようとする勇気ある試みであった。脚本は細部では欠陥があったものの、全体としては正確で、事件をめぐる論争に歴史的な貢献ができるはずのものであった。しかし、ストーンは彼の信頼性を損なおうとするメディアの企ての後、脚本を書き直したと発表した。このため、「JFK」は違った意見を調和させる試みとなってしまい、歴史よりも、興行成績と映画評論家の利益に奉仕するものとなった。
この様に、映画「JFK」は両サイドからの集中攻撃を受けながらも完成した。しかし冷静にこれらの状況を考えてみると、ワシントンポストやニューヨークタイムズがこの映画製作の進行をこれほどまでに速い段階から妨害もしくは潰しにかかったことは、映画の正確さ、もしくは批判者、特にラードナーの批判の正確さをしめすものではなく、この映画の持つ本質的な重要性を示しているのではないだろうか。映画検閲の是非を問うまでもなく、映画は人々の一般の関心を高めると共に、無制限の力を行使している者たち、つまり情報機関やマスコミの特定の利害を暴露してしまうからであろう。現実に数百万いや数千万の世界の観客がこの映画を見る、という事実は特定の利害者にとっては恐怖以外の何ものでもなかった可能性は決して否定の出来ない事実ではないだろうか。
オリバー・ストーンは映画のクライマックスでジム・ギャリソンに次のように語らせます。・・・・
我が国のある自然主義者は言っています。”愛国者たる者は常に自分の国を自分の政府から守らなければならない”と、皆さん(ここでは陪審員)にとくと考えて頂きたい。子供の頃、この法廷にいるほとんどの人はこう思われたことでしょう。正義は自然に生れるもので、美徳は必ず報われ、善は必ず悪に勝つと。でも成長するにつれ、これは真実ではないと気ずく。”フロンティアとは人が事実に直面する所だ。”正義とは個々の人間が生みださねばならぬもので、これは生易しいことではありません。なぜなら、真実は権力にとってしばしば脅威となり、われわれは、その真実ためには非常な危険をおかして権力と闘わなければならないからです。・・・・自分達の国を取り戻したがっている、自分達の信じることのために敢然と戦いさえすれば国を取り戻せるからです!真実はわれわれにとって最も貴重です。もし真実が無力になり、政府が真実を抹殺し、これらの人々(捜査に協力した人々)の気持ちを尊べないのなら、最早、ここはわれわれが生れた国ではなく、ここで死にたいと思う国ではありません。ジョン・F・ケネディの場合がまさしくそうだったのです。
|

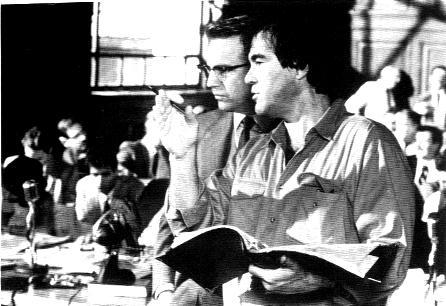 ザーランド、その他のスター達の役にたてるのか?たとえば、現実に陰謀が存在し、それがギャリソン/ストーンが割り出したものでなかったらどうであろう?
ザーランド、その他のスター達の役にたてるのか?たとえば、現実に陰謀が存在し、それがギャリソン/ストーンが割り出したものでなかったらどうであろう?